独占業務
行政書士には独占業務が与えらえています。
他人の依頼に基づいて官公署に提出する書類や権利義務・事実証明に関する書類(電子データ含む)作成を有償で行うことは行政書士しかできません。(他の法律で制限されているものは除く。弁護士法、税理士法、司法書士法等…)
これまでも独占規定はありましたが、今年1月から「いかなる名目によるかを問わず」という文言が追加(施行)され、これまで(違法な)コンサル業者がよくやっていた「書類作成支援」「申請サポート料」といった名目が通用しないことが明示された訳です。
それに伴い、行政庁の間で改正行政書士法施行の通知が飛び交い、例えば警察署から自動車ディーラーに注意喚起の案内が行ったりしているようです。
ところが、これには不安な要素もあります。車庫証明等、多くの行政書士が扱っている分野でしたら特に問題はないのですが、幼保分野のように、ほとんどの行政書士が扱わない分野で、これまでコンサル業者が主に担っていた分野の場合、いきなり行政書士に依頼してもまともに業務を行えないケースがたくさん出てくると思います。
例えば何でもやりますと謳っている新人さんに保育所の認可申請業務の問い合わせがいったとして、見通しを見誤り、無理筋の案件を受任してしまったら、依頼者も当人も破綻してしまうことになりかねません。それなら最初から知識の豊富なコンサル業者に相談して、早めに無理だと判断してもらったほうがお客様のためになる訳です。
個人事務所の場合、扱える数も種類も限りがあるので、どうしても専門特化するほうが効率がいいのは仕方ないのですが、せめて自分が扱えない分野の問い合わせが来たとき、他の事務所を紹介できるように支部活動などで横のつながりを持っておくことは大切だなと思います。
あとは医療や保育・障害・介護といった福祉関係を始めとする、あまり行政書士が参入していないけどお客様が困っていてコンサル業者に頼り切りな分野に興味を持って本気で勉強する新人さんが増えてくれるといいなと思います。
ちなみにこのような書き方をすると、コンサル業者を否定しているように思われるかもしれませんが、決してそんなことはなく、むしろ保育業界においてはコンサル業者の存在がとても助かっていたります。実際に園舎建設といった大きな案件の場合、コンサル業者と分担・協力して進めることが多いのも事実です。最終的にはそこに通う子どもたちの利益を考えられる業者と協業していけたら素敵だなと思っています。
特定行政書士 寺島朋弥
2026年1月20日
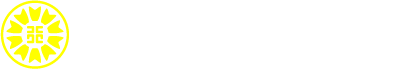
 03-5948-4231
03-5948-4231

