今回の法改正で、全ての学校法人が計算書類(決算書)等をインターネットで公表しないといけなくなると誤解されている方が案外いらっしゃるようです。
確かに新法151条には寄附行為や計算書類、財産目録等の公表義務の規定がありますが、これはあくまでも大臣所轄学校法人等(大臣所轄法人と一定規模以上の知事所轄法人=幼稚園単体の場合はまず該当しない)の義務であり、幼稚園単体のような知事所轄学校法人に対する義務ではありません。
そして新法137条のほうにも寄附行為や計算書類等のインターネット等での公表の規定があり、こちらは全ての学校法人が対象ですが、条文の結びが「公表するよう努めなければならない」となっており、これは努力義務と言い、公表の義務ではなく、公表する努力をすることが義務なのです。
※法律の建付上は、努力義務が原則で、大臣所轄学校法人等は特例で義務という形になっています。
細かいことのようですが、法律の世界、特に行政法界隈では、義務と努力義務の違いは大きく、明確に区別されています。
ところが、文部科学省が出している寄附行為作成例では、知事所轄学校法人向けのものでもここに関する規定(作成例69条)が公表義務になっているのです。そして、各都道府県の作成例もそれに倣っているため、多くの人が法律の条文ではなく、寄附行為作成例を見て、義務化されたと勘違いされているようです。
問題はいくら法律で努力義務となっていても、寄附行為で義務と規定してしまうと、本当に義務になってしまう点です。この場合、公表しないと法律違反ではなくても、寄附行為違反となり、執行部の責任を問われたり、行政指導の対象になったりし得ます。
私は別に義務ではなく努力義務なのだから公表する必要なんかないと言いたい訳ではありません。私学助成といった補助金をベースに運営されている訳だから、むしろ公表するのが自然かと思っています。(実際、社会福祉法人はどんなに規模が小さい法人でも定款や計算書類等は丸見えですし!)
しかし、法律殊に行政法の実務家として、法律で義務化されていないことを、寄附行為でこっそりと義務化(一般の事務職員だけで対応している法人さんの多くは気づかないと思います。)させるような行政の動きに違和感を覚えてこの記事を書いた次第です。
実は今回の寄附行為変更(作成例)は、これだけに限らず、結構落とし穴があります。まだ時間はありますので、じっくりと見直されることをおすすめします。
また、有料とはなりますが、寄附行為変更案のチェックや相談だけでも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。(今月は本件に関する業務が立て込んでおりますので、多少お待ちいただく場合がございます。)
特定行政書士 寺島朋弥
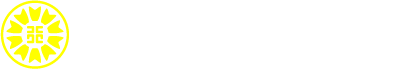
 03-5948-4231
03-5948-4231

