幼保行政書士の移動手段
この記事はどちらかというと、東京23区でこれから開業する同業者で、幼保関係に関心がある方向けの記事です。
さて、行政書士の移動手段は、全国的に見たら自動車が圧倒的に多いのは言うまでもないでしょう。しかし、都市部の行政書士は、電車・バスによる移動が多いのが実状かと思います。
そもそも都市部(特に東京23区)での生活は、プライベートでも車を必要としないので、そもそも車を持っていないことも多いと思いますが、幼稚園・保育園系の手続書類はいまだに押印書類(つまり紙媒体)も多く、ファイルも分厚いことが多いので、私は結構車を使うことが多いです。
都心部での車移動で一番気がかりなのが、駐車場探しです。料金が高いのはともかくとして、一番の問題はそもそも駅近は満車だらけで、空いてるところを探して延々と時間を浪費してしまう恐れがあることです。それによって遅刻などとんでもないので、極力予約制の駐車場を使うようにしますが、お客様の園の立地によっては、付近に予約制駐車場がない場合もあります。そういう園への訪問は、そもそも電車を選択します。
ちなみに、幼稚園はどんなに都心部であっても駐車場付き(敷地内になくても付近の園バス駐車場に余裕があったりする)がほとんどなので、基本的に心配いりません。逆に保育園の場合は、保護者さんであっても車での送迎禁止が当たり前で、近づくことすら難しかったりするので、初めて行くところはリサーチが必要だったりします。
行政書士業務も分野によってはほとんどオンライン化され、PC1台で、場合によっては移動もせずに事務所内でほとんど完結することもあると思いますが、保育や特に幼稚園はまだまだ書面主義であり、また、不動産まわり等現場に触れないと分からないことも多かったりするので、結構移動することが多いです。(ハンズフリーで移動中に電話に出られるのも車移動のメリットです。)
ところで、私の場合、5・6月が保育園(社会福祉法人)に集中しなければならない反動で、7月はその間にスポットで受けていた幼稚園三昧になる傾向があり、暑い時期にエアコンが効いた状態で悠々と移動できるのでありがたいなと思うことが多かったりします。もっとも、園によっては夏休みまでにどこまで進められるかという問題も出てきて、7月に幼稚園を集中させ過ぎると大変なことになるので要注意ではあります。
特定行政書士 寺島朋弥
2025年7月15日
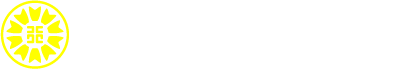
 03-5948-4231
03-5948-4231


