行政書士事務所と雇用
行政書士業界は、他の士業と比較して従業員の雇用が極端に少ないと言われています。
昨年日本行政書士会連合会が実施した行政書士実態調査の集計結果によると、補助者を1人以上雇用している行政書士は22.3%となっていますが、そもそもこの調査への回答は任意であり、回答数(母数)は3084人。5万人中3千人、つまり全体の6%しか回答していない調査です。そして、こういった調査に回答する行政書士は、いわゆる「意識の高い」行政書士が多いと思われ、その中でさえ補助者雇用が2割ということは、全体では更に低いことが推測されます。
他士業では、試験に合格したあと、登録する前に一定期間事務所での勤務(修行)経験が必要な場合がありますが、行政書士ではそれは成り立たないということで、別の考え方をすれば、修行する機会がなく、実務経験ゼロのまま開業せざるを得ない人が多いということでもあります。
私は補助者さん(内一人は行政書士志望)と一緒に仕事をしておりますが、業務量的に必要だということも勿論ありますが、同時に行政書士志望者については若い芽を育てたいという意識も持っています。
支部などで同業者と交流していると、実際出会う人の8~9割はお一人で経営されている印象を受けますが、決してそれを否定するつもりはありません。一人で十分こなせる業務分野もありますし、そういった方は、大きな案件は同業者同士でチームを作って共同受任するなどして、上手にこなされているので、それも立派な経営手法だと思います。
私の場合は、繁忙期の業務量的に補助者が必要不可欠ということもありますが、おそらくプライベートを犠牲にして死ぬ気でやれば一人でもできますし(新人の頃保育の認可案件を一人でこなした経験あり)、そのほうが同じ売上高でも所得が増えるのは間違いありません。それでもあえて通年雇用し続けている理由は三つあり、一つ目は先に挙げた理由(若者育成)と、二つ目はプライベートを大事にしたいからです。
我が家には小学3年生と年長組の二人の子がおりますが、子どもの成長は儚いもので、瞬く間に大きくなっていき、今この時の姿は二度と戻ってくることはありません。仕事と家庭を両立したいから、業務の一部を補助者さんに手伝っていただいているのです。そして、子どものイベント参加や通院のために事務所を留守にするときに、あえて補助者さんに正直に伝えているのも、自身が将来経営する立場になったときに参考にしてもらいたいという思いもあったりします。
そして三つ目の理由は、お客様である経営者と共感するには、自分も同じ重圧を感じ続けるべきだと思うからです。雇用を続けるためにはそれなりに売上を出し続けないといけません。特に労働集約型のサービス業だと人件費比率が高いので、仕事を取り続けないといけないという重圧感は半端ではありません。そういった環境に身を置いたことがある人にしか分からないことは確かにあり(言葉では説明不可能)、そのことで共感することにより互いにリスペクトし合うことができる部分が確かにあることを日々経験しているからです。
これから経営者さんを相手にする仕事をしたいと思っている新人同業者さんがこの記事を参考にして、自身の将来の経営方針に役立ててもらえたら幸いです。
特定行政書士 寺島朋弥
補足
こういった事務所経営の記事をご覧になり、うちで働きたいというご連絡をいただくことがあるのですが、申し訳ございませんが臨時の採用は行っておりません。うちも零細事務所でしかなく、専門分野(幼保)の特殊性からもこれ以上の採用はとても考えられませんので、その点はご理解いただければ幸いです。
2024年7月30日
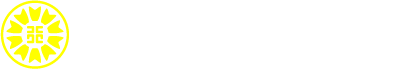
 03-5948-4231
03-5948-4231

