地方行政の問題
幼児教育・保育分野を取り扱う行政書士が少ないせいもあり、地方の保育行政に関わる案件の場合、びっくりするような事態に遭遇することが多いものです。
まず、行政書士の存在すら知らなかったり、民法上の「代理」の概念すら正確に理解していない役人が多いのはまぁまぁよくあることなので驚きませんが、中には行政作用(行政行為)の概念から丁寧に教えてあげないと話が進まないなんてことも。そういったところは、当然のことながら、保育制度の複雑な法体系など理解どころか知らないケースすら現実にあるのです。
では彼らはどのように仕事を進めているかというと、要綱とったいわば行政内部のマニュアルの通りに事務手続きを進めているだけだったりします。首都圏では、こういった要綱までデータベース化されてインターネットで公開されたりしていることもあり、かなり精度の高い規程になっているのが普通ですが、先に挙げたような自治体ではこれもまたお粗末で…。具体例は挙げませんが、びっくりするような誤りや、いかようにも解釈できるとんでもない条文も散見されたりします。
これが普段行政書士といった民間の専門家が関わってくることのない地方行政(保育といった特定分野だけの話と信じたいですが)の現実です。
同業者から行政作用だの不服審査関係だの、受験生並みによく覚えてますねと関心されることもありますが、こういった地方行政を相手にしていると普段から活用しまくる必要があるので、忘れるどころか日々アップデートが必要になる訳です。
誤解しないでいただきたいのは、私は別に地方行政全体をバカにしている訳ではなく、地方でもとても有能な担当者がいらっしゃり、気持ちよく仕事を進めることができることもあります。逆に東京23区内でとんでもない担当者がいらっしゃることも…。(苦笑)
あくまでも傾向として、町・村を含む人口の少ない自治体は、先に挙げたようなケースに遭遇する確率が非常に高く、苦労してきた現実があるということです。
本来、行政はどこに住んでいても、どこで事業をするにしても、公平であるべきです。それが、行政担当者の未熟さが原因で、不当に国民の権利利益が害されることだけは絶対にあってはならないと考えています。それを是正するのも、我々専門家の使命だと思っています。
おそらく幼保分野に限らず、あまり行政書士が参入していない分野の業務は、どれも同じことが言えると思います。こういう時こそ、行政書士試験で学んだ行政法の知識を大いに活かせるので、若手こそ未開拓分野に取り組んでいただきたいものだと思っています。
また、現在の受験生も、行政法なんて実務で役に立つのかなと思っているかもしれませんが、11年間ずっと駆使し続けている私が言うので、特定分野では役に立つと保証します!本試験まで残り2ヶ月、夢を抱きつつ頑張ってください!
特定行政書士 寺島朋弥
2025年9月11日
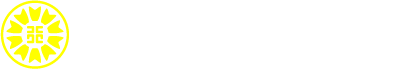
 03-5948-4231
03-5948-4231

