【改正私学法】現行役員等の任期について
学校法人制度改革について、どこも対応の真っ最中かと思います。
今回は理事・監事・評議員(以下「役員等」)の新制度移行期の任期について解説してみようと思います。
来年4月から改正法が施行されることになりますが、大前提として来年6月に行われる定時評議員会終結時までに、役員等のそれぞれの要件を満たしている人に統一する必要があります。言い換えれば、現時点で改正法の役員等の要件を満たしていない人は、来年の定時評議員会終結時点までに要件を満たさない限り、続けることができないということです。したがって、現在の役員等の全員が選任要件を満たしていることが前提となっていることをご承知おきください。
さて、法改正時の移行期は、様々な問題や矛盾点が発生するものですが、現行役員等の任期もその一つです。これまでの学校法人は、任期については寄附行為自治が認められており、無期限も有り得ましたが、改正法では寄附行為自治ではあるものの、法定上限があり、理事は4年、監事と評議員は6年が上限となり、その期間内で寄附行為で定めるのは自由ということになっています。個人的な感触では、上限ぎりぎりを定める法人が多いように思います。
そうなると、現在無期限であったり最近選任(重任)され、まだまだ任期が残ってる人がどういう扱いになるかということが問題になると思います。答えは、次のいずれか早い方までということになります。
- 現在の任期満了日
- 令和9年6月の定時評議員会終結の時
当然ですが、現在無期限の人は、2が適用されることになります。
以上が法令の解説というか、原則論です。しかし、これを原則どおり適用するだけで何も手を打たないでいると、法人によっては役員ごとに任期がバラバラになり、毎年のように選任手続きが必要な状態になってしまうケースがあるので要注意です。
そこで、そうなり得る場合に私が顧問先におすすめするのは任期調整です。簡単に言えば、最初の選任手続きが起こる時に、役員等全員に一度辞任していただき、あえて全員を改選することで任期を揃えることができます。正確には違いますが、強引に言えば解散総選挙みたいなイメージです。
しかし、こういったテクニックを使う場合は、何ヶ月も前から事前調整(根回し)が不可欠ですし、手続きの書類に一つでも問題(漏れや期限遅滞等)があれば、最悪の場合、後々法的に無効になることだってあり得るため十分な注意が必要です。ちょっと変わったことをやる場合は、まずは相談だけでもいいので専門家の知恵を借りることをおすすめします。
当事務所はこういった事案の対応経験は豊富で、相談だけでもお受けしておりますので(ただし本事案のような個別具体的なケースは初回から有料です)、お気軽にご連絡ください。
特定行政書士 寺島朋弥
2024年7月19日
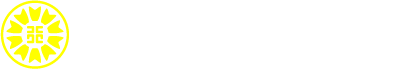
 03-5948-4231
03-5948-4231

