ふと思い立ったので、認可保育園(保育所や地域型保育事業を総じてこの記事では「認可保育園」と言います。)の新設案件の行政手続きの実情について書いてみようと思います。
行政書士の王道業務は「許認可」であることは言うまでもなく、その「認可」という文字があるとおり、認可保育園の申請は行政書士業務と言えます。ところが、実際にこの業務を経験したことがある行政書士はとても少ないです。
HPなどでいろいろ解説してあるのを目にすることがありますが、経験者からすると「ん??」と思うような内容も多々あり、大手さんは別としてフルで携わった経験のある同業者はそれほど多くないのではと思っています。
計画から1年程度で完結する地域型保育事業(いわゆる小規模認可保育園=以後「小規模園」とします。)は経験したことがある同業者と話したことはありますが、2~3年かかる認可保育所(0~6歳まで100人くらい預かるような規模の認可保育園)をフルで経験したことがある人とは直接お会いしたことはありません。(大手事務所さんはチームで実際にこなしていると思います。)
それでは、この10年で無数の認可保育園が立ち上がりましたが、申請業務は誰が担っていたのでしょうか。
私のこれまでの経験からまとめると、認可外から小規模園単体を作ったという話であれば、経営者さんが自ら頑張って申請書類を作成し、行政手続きをされているケースが多いです。中には職員である保育士さんまで巻き込んで、夜中まで残業して書類作成をしたという話も実際に聞いたことがあります。
次に、小規模園を多数展開しているような株式会社さんの場合は、自社内に行政手続きの部署を設置し、人海戦術で行っているケースをいくつか見てきました。
最後に、大規模な施設整備(建設工事)が伴う案件の場合は、ほとんどは設計業者さんや、保育事業のコンサルタント会社が「サポート」しています。その場合、有料で書類作成を行ってしまうと行政書士法違反になるため、(作成は)無料であったり、(作成はせずに)支援であったりと上手いことやっています。※そういった案件が途中で頓挫しかけて私が引き継いだことがあり、契約内容含めて実情も把握しています。
しかし、私はそのことで行政書士法的にどうなのかとか、とやかく言うつもりはありません。一番の問題は、大型の認可保育園案件に対応できる行政書士が少なかったことにあると思っているからです。そして、今後も認可保育園案件が続くのならともかく、少子化の影響で新設案件は現に急激に減っているので、今更この業務について学ぼうとする同業者が出てこないのは仕方のないことだとも思っています。
そういう状況で私ができることと言えば、新人の行政書士が関わるチャンスがあるのであれば積極的に受けるようアドバイスし、場合によっては共同受任すること。そして、大型案件をゼロベースから手伝った経験のある現補助者さんが将来資格をとって独立するのであれば、同じレベルの仕事ができるようにノウハウを引き継げるようにしておくこと。といったことかと思っています。
認可や確認の変更手続きであったり、監査対応であったりと、既存園の行政手続きに関わる機会は数多くあるのですが、やはり新設認可申請の経験があるかどうかはとても大きいことだと思います。というのは、認可案件は、全てがスムーズに行くなんてことはなく(少なくとも私はそんな経験ありません)、想定外のトラブルのオンパレードです。それらを対処するノウハウは、変更手続きなどで想定外のことが起こったときに応用がきくケースが多いので、トラブル経験はあるに越したことはないと思っています。
私は10年間で10件以上の新設案件にせっかく携わらせていただいたのだから、その経験を活かしていけたらと考えています。
特定行政書士 寺島朋弥
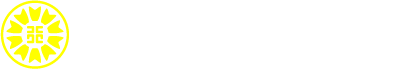
 03-5948-4231
03-5948-4231

