社会福祉法人の設立
ごくまれに、株式会社のお客様から「社会福祉法人を作りたい」とアバウトな相談を受けることがあります。
社会福祉法人は非営利法人ではあるものの、一般社団法人やNPO法人とは違い、作りたいからと言って作れるものではありません。大前提として、社会福祉法に定められている社会福祉事業を行うことを目的とする法人なので、社会福祉事業を既に実施していたり、ほぼ確実に実施できることが見込まれれる状態でないと認可されません。その社会福祉事業は公金(補助金)がないと回らないものばかりですので、公的機関からの信用がないとまず無理です。
そして、原則として社会福祉事業を行うための不動産を所有(賃貸借ではダメ)する見込みがあるか、施設が不要な場合は1億円以上の現金を寄附により保有できる状態である必要があります。(この時点で大抵の方は諦めます)
続いて人的要件として、理事6人以上、監事2名以上、評議員は理事の人数+1人以上(ちなみに評議員全員で構成される評議員会が理事の選任権を握っている)、その評議員を選任するための要員が少なくとも追加で2名ほど必要であり、理事と評議員(株主や社員に近いけど全然違う存在)は兼ねられないどころか、評議員には理事の親族すらなれないと聞いた時点で大抵相談は終わります。
資本を投下して事業で増やして儲かるという、ビジネスの常識から考えると何の意味があるの?と思ってしまうのは当然です。
先ほど社会福祉事業の実施が見込まれる必要があると記しましたが、認可保育園の一例を挙げると、行政の公募を通っていて、児童福祉審議会の承認を得て、なおかつ施設の建設費の補助金(数億円の補助金)の内示が出ていて、数千万円の自己負担分を持っているか、借入できることが確実(例:福祉医療機構の受理票が発行)といった要件が全て揃って「見込まれる」と判断される訳なので、確実に認可保育所を建設し、自己所有できる状態まで持っていって初めて社会福祉法人の設立認可が出るということなのです。
通常、最初の計画からここまでに1年半~2年はかかります。その間幾多の試練を乗り越えて、ようやく法人設立の認可申請ができるということなのです。
ちなみに、弊所では認可保育所の社会福祉法人しか扱いません。(一応小規模保育事業であっても定員10人以上であれば社会福祉事業に該当しますが、その事業単体で社福を設立する話は聞いたことがありません。)
その理由は、社会福祉法人の設立は、実施を予定している社会福祉事業の事業法(保育であれば児童福祉法や子ども・子育て支援法)とも密接な関係があり、その分野の専門的な書類作成が多数あるため、専門外の分野の法人には関与できないことをよく知っているからなのです。
高齢者福祉や障がい福祉関連事業者からのお問い合わせを一律でお断りしているのは、それが理由ですのでどうかご理解いただければと思います。
ちなみに社会福祉法人の設立は、どんな法人であってもドラマがあり、とても大変ですがやり甲斐のある仕事です。少子化の進行により、保育事業での社会福祉法人の設立は今後ますますなくなっていくことは避けられないでしょうけど、お話があれば喜んで伺いますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
特定行政書士 寺島朋弥
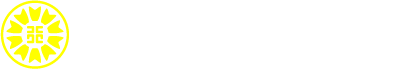
 03-5948-4231
03-5948-4231


■コメント
コメントはありません
※申し訳ございません、現在コメントフォームは閉鎖しております。