幼稚園と相続
昨今の認可保育園や介護事業等いわゆる補助金事業の常識をご存知の方からは意外に思われるのですが、私立幼稚園には個人事業主によって設置され、運営されているところがまだまだ存在します。(経緯は割愛しますが現在は個人による新規設置は不可能。)
幼稚園に限らずどんな個人事業でも共通ですが、その事業主が亡くなった時の対応が問題になります。財産云々の部分は相続ということになりますが、例えば従業員を雇用している場合の雇用契約関係、顧客との契約関係、行政から補助金を受けている場合のその権利関係等、権利主体である個人の死亡によってあらゆる法律関係がリセットされることになります。
特に公的な色の強い学校(幼稚園)の場合、相続というよりも設置者が変更されるという概念になるため、行政手続きの観点でも非常に面倒(書類の数で言えば新規設置に近い量の書類が必要)なことになるのです。私も年に1~2件は幼稚園と相続の相談をお受けしておりますが、複数の専門家が共同して取り掛かる一大プロジェクトになってしまうことも多々あります。
相続手続自体は私は専門ではないので基礎知識程度しかありませんが、相続だけでも場合によっては全国各地に住んでいる十人以上の相続人から実印や印鑑証明書をもらったり、家庭裁判所の手続きが絡んだりするケースもあり得るというのに、早急に行うべき幼稚園の設置者変更認可申請で何十枚、場合によっては100枚超えの申請書を準備するなんてとんでもない負担になることでしょう。
それらを少しでも軽減するためには、可能であれば事前に事業継承をしておくか、代表者のままでいたいのであれば学校法人を作っておくということになります。事業継承であれば、設置者変更認可の手続き自体はほとんど変わりありませんが(相続書類の添付がない程度)、相続と同時でない分、負担は軽減されることになります。
学校法人化は、正直なところ作る時の手続きは設置者変更の比ではなく非常に大変ですが、その後は恒久的に経営主体が変わらないことになるので(ご本人が亡くなっても理事長が変わるだけ。理事長変更の手続きは手数はあるけど簡単。また代表権者を同時に2名以上置くことも可能なので緩やかに引継ぎもできる。)、子孫のことを考えると十分検討に値すると思います。
幼稚園経営であれば公認会計士さんや税理士さんと並走していることと思いますが、行政手続きの観点で検討段階から一緒に相談に応じることも可能ですので、事業継承の準備をお考えの場合は、お気軽にご相談ください。
特定行政書士 寺島朋弥
2025年1月27日
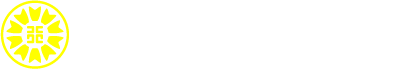
 03-5948-4231
03-5948-4231

