【改正私学法】理事の選任方法
令和7年4月1日施行の改正私学法について、実務を進める中で思いついた時に気まぐれに書いてみようと思います。体系的に連載する予定はありませんのでご了承ください。
さて、今回の改正で一番大きな変更点といってもいいものは、理事の選任機関の設置ではないでしょうか。おそらく、現在多くの法人さんでお困りのことと思います。
あくまでも私の見解ですが、幼稚園や認定こども園では評議員会を選任機関にしたらいいと思っています。他に考えられることとしては、理事選任・解任委員会のような機関を別に設置し、そこに委ねるといった方法もありますが、その機関を運営するための規則が必要になったり、委員の管理や会議を開催するための手続きが増えることになります。(ここではあえて書き(け)ませんが、そうすることによる経営陣にとってのメリットもデメリットも当然あります。)
しかし、どうしても小規模法人である幼稚園や認定こども園の場合、いろいろ小細工をして手続きを複雑化するよりも、ストレートに評議員会に委ねるのがいいと思うのです。他の機関を置いた場合でも、結局のところ評議員会の関与(諮問)は必要ですので、それならば建学の精神に共感してくれる信頼できる評議員を集めて、その方たちに委ねるという形が健全ではないでしょうか。
ちなみに私は保育所や認定こども園を運営する社会福祉法人とのお付き合いが多く、2017年の制度改革の際にも関与していますが、社会福祉法人の場合は理事・監事の選任・解任権限は評議員会と法定されているため、動かしようがないのですが、少なくとも私が関与しているところは健全な運営ができているところばかりです。
中には評議員会で評議員が理事長を含む理事に対して意見・注文を付けるような場面もありますが、子どもたちの最善の利益を追究するという共通の目的がある限り、それは健全な議論であり、対立関係ではありません。これからの学校法人は、現在の社会福祉法人と同様に、理事が自分たちの教育・保育方針(もちろん収支も大事ですが…)について自信を持って評議員会に説明し、それを理解していただくことで身分を保証(理事に選任される・解任されない)してもらうという形を作っていくべきではないでしょうか。
最後はほとんど私の個人的な思いになってしまい恐縮ですが、各法人の寄附行為作成に向けての参考にしていただければ幸いです。
なお、類似の懸案事項として、評議員の選任・解任はどうするのかというのがあるかと思います。この点についても社会福祉法人制度も参考にはなりますが(とはいえあちらもこの点は定款自治の範囲)、学校法人ならではの設計ができると思っており、とても興味深く思っているところです。また気が向いたら事例や考え方をまとめて書いてみたいと思っています。
特定行政書士 寺島朋弥
2024年4月24日
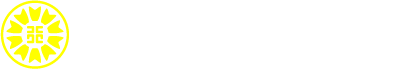
 03-5948-4231
03-5948-4231

