非弁とモームリ騒動
退職代行業者モームリに非弁疑いで家宅捜索が入ったとニュースになっていますが、退職代行が流行りだした数年前から、サービスの内容を聞く限りそのうちこういうことになるだろうなとは思っていました。
非弁というのは非弁護士のことですが、弁護士法違反という意味では大きく分けて非弁行為と非弁提携があり、今回の事件は主に後者のようですが、一部前者に関わる証言も報道されているようでした。
ちなみに、非弁提携とは、弁護士と提携し、事件を弁護士に紹介する代わりにキックバックを得るという行為のことで、困っている人に知人の弁護士を紹介するだけであれば問題ありません。我々のような弁護士以外の士業は、大抵信頼関係のある弁護士の知人がいるもので、自分のお客様が法律トラブルに巻き込まれたときに、信頼できる弁護士を紹介をする(当然紹介料等の授受は一切無く、その後事件に関与することも無し)ということはよくあるもので、そういったことを禁止している訳ではありません。問題となるのは紹介による見返りがあることで、弁護士側も犯罪に当たるのが通常です。(実際今回も弁護士事務所も捜査されているようです。)
もう一つの非弁行為というのは、弁護士以外が(事件性のある)法律事務を扱うことです。事件性云々は大事なポイントなのですが、諸説あるためここではあえて論じません。要するに素人が法律事務を行うことは違法行為ということです。
モームリ社の言い分は「退職意思の通知しかしてないので非弁ではない」ということのようですが、退職意思の通知は、労働契約の解除通知という立派な法律行為です。法律行為を人の代わりに行うことは、「代行」ではなくもはや「代理」にあたり、他人の法律事務を扱っている事実があることになります。(非弁ではないという主張は、事件性必要説に立っての主張と思われますが、先ほどと同様ここでは論じません。)
ちなみに行政書士をはじめ、いわゆる士業の業務はほとんどが法律事務です。例えば行政書士であれば、許認可申請の代理は立派な法律事務ですし、特定行政書士が行う行政不服申立ては行政機関と争うという、事件性のある法律事務ですが、弁護士法の中で「他の法律で認められてるならやってもいい」という部分があるからできていることです。
要するに国家資格等、法律の後ろ盾があれば、慎重にその範囲内で業務を行えば問題ないのですが、この論点だけでも無資格の一般事業者が法律に関わる仕事をするのは大きなリスクがあることが分かると思います。
とはいえ、ブラック企業でギリギリの生活で働かされている若者が、弁護士にアクセスするのは容易ではないことも事実で、その意味では社会全体の問題とも言える側面はあると思います。一般市民が法律サービス(弁護士だけでなく他の士業も含めて)に気軽にアクセスできる仕組みを整えることも社会の責務だと思うので、無料相談会の相談員といった会の仕事もできるだけ関わらないといけないのだろうななんて思ったりしています。
特定行政書士 寺島朋弥
2025年10月23日
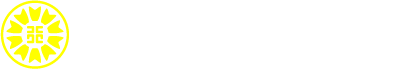
 03-5948-4231
03-5948-4231

