本日、保育士の人件費を10.7%引き上げることを国の経済対策に盛り込むという報道がありました。
職員(保育士資格者以外の保育補助者・調理員・看護師・事務職員等全て含める必要あり)の人件費を大幅に上げること自体は大賛成です。そのうえで制度設計時に考慮してもらいたいことは、必ず人件費として使うように制限をかける必要があると思います。そして、処遇改善等加算Ⅲのように、手厚い配置をすればするほど、一人あたりの取り分が少なくなるような仕組みではなく、具体的な数字を出す以上、全て職員に平等に行き渡るようにして欲しいものです。
そして、その賃金上昇を実現できるのであれば、ぜひ人材紹介業者の規制も併せて検討して欲しいものです。現在、常勤保育士を1人雇用するためには、軽く100万円以上の手数料がかかります。赤字経営の法人でも、人材紹介業者に支払う手数料さえなければ黒字という法人は実際に存在しており、そういった法人は、結局人件費を圧縮するしかありません。手数料は雇用する保育士の年収がベースになるため、賃金が上がればその分手数料も上昇し、ますます保育事業者の経営が厳しくなることが目に見えています。
人材紹介業者から貰える「お祝い金」欲しさに転職を繰り返す保育士さんも、結局は保育職員全体の賃金を圧縮することにつながっている現実を、是非認識していただきたいところではありますが、国にはこのあたりの実態をしっかり調査して、施設に給付した補助金等が当たり前に人件費に回って、無駄な流出がないかチェックして、必要な対策を行っていただきたいものです。
なお、毎週のようにお客様の現場に通ったり、保育者向け研修会などで現場職員の生の声を聞いてきている者としてあえて言わせていただきますと、低賃金に困っているという現場の声は案外少ないもので、それよりも余裕を持って保育にあたれるように配置基準を改善して欲しいという声のほうが圧倒的に多いと感じています。
1~2歳児6人を一人で見たり、まだまだ第一次反抗期の3歳児20人を一人で見るというのがどういうことか想像してみてください。保育士は国家資格者であり、保育のプロという前提はあるものの、3歳児が20人いる実際の現場を、是非制度設計をする役人さんたちにも見て欲しいものです。その際は、彼女ら彼らは、自分が楽をしたいから言っているのではなく、子どもの安全を考えて、かつ一人ひとりの子どもと丁寧に向き合いたいという思いでそれを言っているということを受け止めて欲しいと思います。
予算編成の際には、今の職員さんの賃金改善はもちろんですが、配置基準の改善も含めて広い意味での処遇改善を図っていただきたいものです。
特定行政書士 寺島朋弥
補足
冒頭の10.7%云々はあくまでも今年度の補正予算案に関する話です。本記事とは別の論点ですが、この補正予算案が順調に通った場合、昨年度同様に4月に遡って大幅な委託費等の収入があり、人件費支出が発生することになるため、各法人の予算も大幅な見直しの必要が生じます。来年度当初予算に合わせて、補正予算も慎重に政治の動向を見極める必要がありそうです。
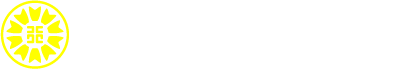
 03-5948-4231
03-5948-4231

