士業の敬称
我々のような士業者の敬称は「先生」となることが多いものですが、私が専門とする幼稚園や保育園業界のお客様からは、そのように呼ばれることは滅多にありません。おそらく、園長先生等の経営者からすると自園のスタッフは基本的にみんな「先生」(幼稚園教諭なんて法律的にもガチで教師)であり、仲間内の呼称といった感覚があるからだと思います。
そういった意味では、私の場合はお客様に対して「園長先生」や「理事長先生」と呼ぶことがあり、私のことをわざわざ先生付けするのは、一部の例外を除いて同業者や他士業者くらいで、補助者さんからも「さん」付けで呼ばれているので、一般的な士業者の感覚とは違うかもしれないと思っています。
また、士業同士が先生と呼び合うのはいかがなものかといった意見を耳にしたことがあり、某SNSのグループでは先生付けを禁止にしているところがあるといったことも聞いたことがありますが、私自身は別に気にしなくていいのではと思っています。お互いに敬意を持つのは社会人として大切なことですし、特に私の場合は日頃から保育園の先生同士が先生付けで呼び合っているのを見慣れているからなのかもしれませんが。
要するに呼称の形ではなく、相手に敬意を払っているかどうかの問題だと思うのです。
特定行政書士 寺島朋弥
2024年10月28日
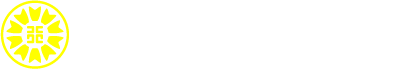
 03-5948-4231
03-5948-4231

