行政書士の代理行為
行政書士は、書類作成だけでなく、他の法律で制限がない限り通常の許認可等の行政手続を代理することができると法定されています。(書類作成や提出は事実行為だから民法上の代理ではないという議論は本記事では考慮しません。)
ところが、私の専門分野(幼児教育・保育)のように、あまり行政書士が関与していない分野の場合、初めて関わる行政の窓口では、結構な確率で「当事者以外の提出・補正は認めない」「行政書士の記名と職印を削除するように」といった指導を受けることがあります。
そこでカッとなっても仕方ないので、根拠法を示して一つ一つ説明していくことになります。代理云々はともかく(法定業務なのでお客様が希望されるのなら当然通しますが)、行政書士の記名(職印)押印は、法的義務(行政書士法施行規則第9条第2項)なので、指導に従うことは法令違反となるため受け止める訳にはいきません。(この点は行政が知らないとは言え法令違反を示唆しているという驚きの状況ではあるのですが。)
なお、行政書士の記名押印は、万が一将来的に紛争が生じた場合、特定行政書士として不服申立てを行うような場合に重要な意味を持つので、法令遵守以外の観点でも死守すべき部分です。その点では、昨今のオンライン申請では、代理人の記名欄がない手続きにおいて、この点に不安があったりします。
ちなみに、建設業許可等のいわゆる王道業務の場合、行政側も行政書士に慣れているので、このようなことは起こり得ないでしょう。様式に行政書士の記名押印欄があったりもするようですし。しかし、それらは先輩行政書士が築き上げた信頼関係あっての賜物だと思います。
私も、将来の後輩行政書士たちが幼児教育・保育分野に参入しやすいよう、今は行政との信頼関係を築く役割を担っているのだと肝に銘じ、日々取り組んでいきたいと思っているところです。
特定行政書士 寺島朋弥
2024年10月11日
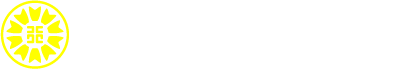
 03-5948-4231
03-5948-4231

