【改正私学法】年度末評議員会・理事会について
学校法人はそろそろ来年度の事業計画・予算の承認に向けて、年度末の評議員会や理事会の準備を始める頃と思います。特に今回は、改正私学法による新寄附行為が施行される直前の評議員会・理事会ということで、注意すべきことがあり、入念に準備をしないといけません。
予算を含む、法改正(学校法人会計基準含む)に伴う会計・経理に関する部分は、顧問の会計事務所さんが相談に乗ってくれると思いますが、ガバナンスに関する部分は法人自身で意識しないといけないこともあるため注意が必要です。今回はこの度の寄附行為変更に伴い、注意すべき2点について記しておきます。
評議員報酬の基準策定
今回の改正私学法では評議員の報酬基準を策定することが義務付けられています。昨年お問い合わせのあったお客様は、令和元年の私学法改正対応で、役員(理事・監事)の報酬基準を策定する際に評議員もまとめて入れておいたため、今回は対応不要といったケースが多かったのですが、中には役員のことしか触れられておらず、評議員については無策定のところもありました。その場合は必ず今年4月1日までに「評議員の報酬基準」を策定・施行しなければならず、そのためには今回の評議員会・理事会の議案にする必要があります。
実務としては、役員報酬規程は既にあるはずですので、タイトルを「役員・評議員報酬規程」など評議員を含む形に変更した上で、内部に評議員に関する規定を盛り込むことになろうかと思います。(評議員は役員ではないため区別されます。)
評議員選任・解任方法に関する細則
各都道府県の寄附行為作成例を見てみると、評議員の選任や解任方法についておおざっぱに定めた上で必要な事項は「評議員選任・解任規程において定める」と規定されているものが見受けられます。こういった規程を委任規程というのですが、寄附行為から具体的な名称を定められている以上、その通りの名称の規程を準備する必要があります。当然、名称だけでなく、具体的な選任方法、解任方法を条文形式で作成していく必要があり、これは私立学校法ではなく、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律を熟知していないと有効な形で作成するのはなかなか困難だと思うので、都道府県がモデル規程を用意してくれないようであれば我々専門家に依頼するのが確実かと思います。(今からの依頼で間に合うかは別問題ですが…)
まずは新しい寄附行為の33条前後にある評議員選任に関する規定をよく見直し、別の規程に委任されていないかを確認し、委任されている場合は必ず4月1日までに「評議員選任・解任規程」を施行しなければならないため、今回の評議員会・理事会の議案にする必要があります。
とりあえず今日の記事では上記の2点に触れましたが、この他にも評議員の損害賠償責任対応やら現行の役員等の構成によっては早速大きく動かないといけない場合もありますので、そろそろ具体的に検討していかないと時間的に厳しくなってくると思います。
寄附行為変更認可申請でご依頼をいただいていた法人様にはこの辺りも含めて対応させていただいておりますが、ご自身で手引き等を参照しながら対応された方は、案外広範囲に影響が及びますのでくれぐれもご注意ください。
特定行政書士 寺島朋弥
スポットのご依頼について
年度末の評議員会・理事会対応については、顧問契約をいただいている法人様で手一杯となっているため、スポットでの対応は難しい状況です。しかし、「評議員報酬は無償」とか「評議員選任・解任方法はできるだけ簡易迅速に対応できるようにしたい」といったご要望で、招集通知や議事録を含まない「議案として乗せるための案」を作成することは対応できる場合もあります。お困りの場合はご相談ください。
2025年2月18日
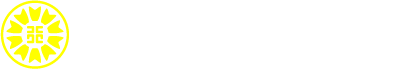
 03-5948-4231
03-5948-4231

