役員変更手続き
社会福祉法人、学校法人等で理事会、評議員会等を取り仕切っていた総務関係の皆様、大変お疲れ様でした。今年は歴史のある社会福祉法人は、4年に一度の一斉改選にあたる法人が多く、学校法人も改正法施行後初めての定時評議員で、諸々調整がある年でした。
特に社会福祉法人は今週頭までの現況報告(財務諸表等電子開示システムでの届出)を終え、今はホッとしていることと思います。
ここで忘れがちなのが、保育側の役員変更手続きです。全員重任であれば手続き不要の自治体が多いですが、中には重任でも届出が必要なケースもありますし、更には保育所の中で一時預かり事業を行っている場合は、それぞれに対して確認変更届が必要だったりするので、保育の認可・確認を管轄する部署に、どのような手続きが必要か、あるいは必要ないのかを確認することをおすすめします。
保育側の役員変更については、届出を怠っていてもすぐには把握されず、行政側からアナウンスがあることはほとんどありません。指導検査の際に発覚し、指摘されてしまうことがほとんどなので、十分注意しましょう。
ちなみに法人側のほうも、自治体によってまちまちです。社会福祉法人の場合、WAM NET(財務諸表等電子開示システム)に最新の役員名簿を常に上げておけばいいという自治体もありますし、いちいち届出書を提出しないといけない自治体もあります。こちらは、調査書等でわりと早めに把握されることが多いので、監査まで放置されて大事になることは少ないかとは思いますが、上記と併せて念のため確認しておくことをおすすめします。
時々弊所にお電話をいただき、「うちは○○市にあるのですが○○の手続きは必要ですか?」と質問される方がいらっしゃいますが、私は全ての自治体を把握している訳ではなく、むしろ全国の1%くらいしか経験ないと思うので、まずは所轄庁に直接問い合わせることをおすすめします。その上で、よく分からないとか、時間がないということであれば、ご依頼をいただければ原則として全国どこでも対応いたします。
特定行政書士 寺島朋弥
2025年7月2日
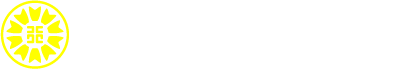
 03-5948-4231
03-5948-4231

