行政書士試験
先週、今年度の行政書士試験が公示され、試験会場等の詳細が発表されました。
今年から試験科目の「基礎知識」のほうに「行政書士法等」が明記され、行政書士の根拠法である行政書士法を学ぶ必要性が生じているようです。どのような知識を問われるのかはまだ分かりませんが、基本的には大賛成です。
よく、「行政書士試験は実務能力が担保されない」などという声を聞くことがありますが、「実務能力」を個別の許認可案件を遂行する能力と定義すると、全くその通りです。
例えば試験に合格して、即独立開業したばかりの行政書士の場合、単純な相続や簡単な契約書作成の相談くらいであれば可能かもしれませんが、行政書士の核心業務とも言うべき許認可案件については、もともとその許認可の根拠法(私の専門で言えば児童福祉法や子ども・子育て支援法等)を学んだ経験がない限り相談を受けることすらできないでしょう。
これは別に新人に限らず、これまで児童福祉に無縁であったベテラン行政書士であっても同じことで、逆に私も建設業許可やら外国人の在留資格といった多くの行政書士が取り扱っている業務であっても、全く相談に応じることはできません。
それでは、行政書士試験は何の能力を担保しているのかという話になりますが、私の考えは「大量の法令や公文書を読み解き、その知識を元に手続きをする能力」と「行政に関わる以上、社会の動きに常に関心を持ち続けて、学び続ける能力」と「基本中の基本のリーガルマインド」という、あくまでも基盤部分の最低限の能力を測っているのだと思っています。その意味では、行政書士法を学ぶということは、実務を行う上で、最低限必要な部分であることは明らかであり、それが試験内容に追加されることは喜ばしいことだと思っています。
行政書士を生業にしていくためには、行政書士試験の受験勉強以上に、実務に直結する法令や制度を学び続けなくてはいけません。試験を突破する力があるということは、少なくともある程度の長期間学び続ける姿勢と能力は担保されていると言えるのではないでしょうか。そういう意味でも、行政書士試験は実務家の最初の関門として、決して無駄なことではないと思います。
今年も私の身近に行政書士試験受験生はいますが、普段はそういった話をしながら応援しているところです。行政書士志望の受験生の皆さんも、将来の学びにつながる勉強だと思って、楽しみつつ頑張ってもらえたらと思っています。
特定行政書士 寺島朋弥
2024年7月22日
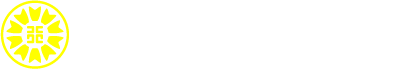
 03-5948-4231
03-5948-4231

